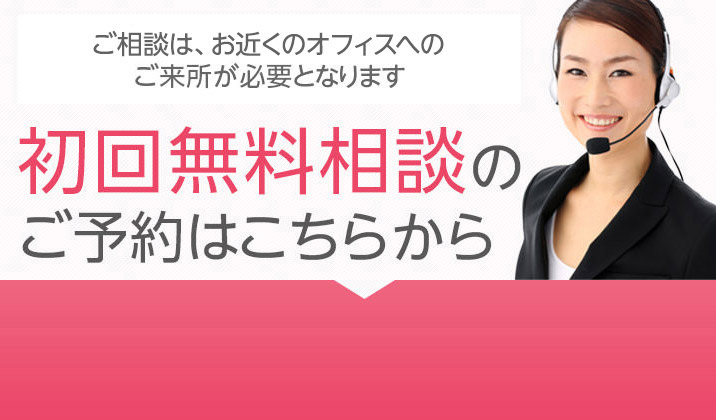離婚時の年金分割に必要な書類とは? 手続きの流れとともに解説
- 財産分与
- 年金分割
- 必要書類

埼玉県が公表している「令和元年埼玉県保健統計年報」によると、令和元年の埼玉県の離婚件数は、1万2067組であり、前年に比べて351組増加しました。離婚率(人口千対)は、1.68であり、全国の離婚率1.69と比べてもほとんど変わりない水準であることがわかります。
離婚時には、「年金分割」という制度があることをご存知でしょうか。専業主婦の方は、第3号被保険者として国民年金しか納めていないという場合が多く、離婚をしてしまうと老後にわずかな年金だけで生活しなければならなくなります。
しかし、年金分割という制度を利用することによって、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割して受給することが可能です。これによって、将来の生活の不安も少しは解消されることになります。今回は、年金分割に必要な書類や手続きについて、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスの弁護士が解説します。
1、年金分割とは
年金分割とは、どのような制度なのでしょうか。以下では、年金分割に関する基本的な事項について説明します。
-
(1)年金分割の概要
年金分割とは、夫婦が離婚をしたときに、一定の条件を満たすことによって、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割し、受給することができる制度のことをいいます。
夫が会社員で妻が専業主婦という夫婦の場合には、妻は、第3号被保険者として国民年金しか納めていないことになります。そうすると、夫婦が離婚をした場合には、妻は、老後にわずかな年金しか受け取ることができずに、経済的に困窮してしまいます。妻は、婚姻中は家事労働を行うことによって夫を支えてきていたにもかかわらず、このような事態になるのはあまりに不合理です。
このような不合理な事態を解消するための制度が年金分割なのです。 -
(2)年金分割の対象
年金分割をすれば相手の年金額の半分をもらえると考えている方もいますが、実はそうではありません。
日本の公的年金は、以下のような3階構造になっています。- ① 1階部分 国民年金
- ② 2階部分 厚生年金
- ③ 3階部分 企業年金
年金分割の対象になるのは、上記のうち2階部分になりますので、国民年金や企業年金は年金分割の対象にはなりません。また、年金分割は、年金額を分割するというわけではなく、保険料納付記録を分割するという点にも注意が必要です。
2、年金分割の種類
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。以下では、それぞれの方法についてわかりやすく解説します。
-
(1)合意分割
合意分割とは、夫婦が合意または裁判によって分割割合を定めて、厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する制度のことをいいます。合意分割をする典型例としては、共働きの夫婦が年金分割を求めるケースです。合意分割の対象となるのは、夫婦のどちらか一方の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)ではなく、夫婦双方の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)の合計額です。
合意分割をする場合には、以下の要件を満たす必要があります。- 平成19年4月1日以降に離婚した夫婦であること
- 夫婦の合意または裁判手続きによって年金分割割合を定めていること
なお、合意分割による分割割合は、当事者または裁判によって決めることになりますが、分割割合の上限は50%とされていますので、これを超える割合を定めることはできません。 -
(2)3号分割
3号分割とは、国民年金の第3号被保険者からの請求によって、配偶者の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を2分の1の割合で分割する制度のことをいいます。国民年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)の被扶養配偶者のことです。簡単にいえば、専業主婦が会社員の夫に年金分割を求めるケースがこの3号分割にあたります。
3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降の保険料納付記録(標準報酬)であり、3号分割をするためには、以下の要件を満たす必要があります。- 平成20年5月1日以降に離婚したこと
- 平成20年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者期間があること
3、年金分割の流れと必要書類
年金分割を行うためには、以下のような手続きを行う必要があります。
-
(1)合意分割の場合
年金分割のうち合意分割を行う場合には、以下のような手続きが必要になります。
① 情報通知書の請求手続き
合意分割を行う場合には、「年金分割のための情報通知書」が必要になりますので、お近くの年金事務所で以下の書類を提出して請求を行います。- 年金分割のための情報提供請求書
- 請求者本人の国民年金手帳、年金手帳、基礎年金番号通知書
- 婚姻期間などを明らかにするための戸籍謄本など
なお、「年金分割のための情報通知書」は、離婚の前でも後でも請求することができます。
② 「年金分割のための情報通知書」の受領
「年金分割のための情報通知書」は、請求から3~4週間で届きます。離婚前であれば、請求した方のみに交付されますが、離婚後であれば、それぞれに交付されます。
③ 話し合いまたは裁判手続きでの合意
合意分割をする場合には、「年金分割の請求をすること」と「分割する場合の按分割合」を決める必要があります。まずは、夫婦の話し合いによってこれらを決めることになります。
夫婦の話し合いによって合意ができた場合には、その内容を書面に残しておきます。
話し合いでは合意ができない場合には、家庭裁判所の調停・審判または離婚訴訟における附帯処分の手続きによって決めることになります。調停、審判、訴訟では、年金分割の割合は、50%と定められるのが一般的です。
④ 年金分割の請求手続き
年金分割の請求は、離婚後に年金事務所に行き、年金分割の請求手続きを行います。合意分割の場合に必要となる書類は、以下のとおりです。- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本など婚姻期間を明らかにできる書類
- 請求日から1か月以内に作成された二人の生存を証明できる資料(戸籍謄本、住民票など)
- 年金分割の合意を明らかにする公正証書、調停調書、審判書など
- 運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
⑤ 「標準報酬改定通知書」の受領
年金事務所は、年金分割の請求を受けると、按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬を改定します。そして、改定後の標準報酬を明らかにするために「標準報酬改定通知書」を当事者それぞれに送付します。 -
(2)3号分割の場合
年金分割のうち3号分割を行う場合には、以下のような手続きが必要になります。
① 年金分割の請求手続き
3号分割の場合には、合意分割のような複雑な手続きは不要で、離婚後に年金事務所に行き、年金分割の請求手続きを行うだけで足ります。3号分割の場合に必要となる書類は、以下のとおりです。- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本など婚姻期間を明らかにできる書類
- 請求日から1か月以内に作成された二人の生存を証明できる資料(戸籍謄本、住民票など)
② 「標準報酬改定通知書」の受領
年金事務所は、年金分割の請求を受けると、按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬を改定します。そして、改定後の標準報酬を明らかにするために「標準報酬改定通知書」を当事者それぞれに送付します。
4、年金分割を弁護士に依頼するメリット
年金分割を弁護士に依頼することよって、以下のようなメリットがあります。
-
(1)年金分割をするメリットがあるかどうかを判断できる
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割する制度であり、保険料納付実績のうち報酬比例部分が多い方から少ない方へと保険料納付実績を分割する制度です。そのため、年金分割をするメリットがあるのは、ご本人が配偶者に比べて厚生年金保険料の支払いが少なかったという場合です。
このように年金分割をすれば必ずメリットがあるというわけではなく、年金分割をすべきかどうかは、慎重に判断する必要があります。
弁護士であれば「年金分割のための情報通知書」などからご本人に年金分割をするメリットがあるのかどうかを正確に判断することができますので、年金分割を検討している方は、まずは弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。 -
(2)交渉や裁判手続きなどによって按分割合の合意ができる
合意分割を行う場合には、話し合いなどによって年金分割の按分割合を決める必要があります。しかし、年金分割の考え方は、非常に複雑ですので、年金分割制度についての理解がないまま、年金の分割請求をしたとしても応じてくれない可能性があります。
弁護士であれば、年金分割を求める相手方に対しても、年金分割制度をわかりやすく説明し、適切な按分割合となるように交渉を進めることが可能です。話し合いによって解決することができない場合には、調停、審判、訴訟などの裁判手続きによって解決を図ることができますので、安心してお任せください。
5、まとめ
将来受け取る年金は、老後に安心して生活するための大事な資金ですので、離婚時には、忘れずに年金分割の手続きを行うようにしましょう。
年金分割は、離婚から2年という期限が設けられていますので、一人で手続きを行うのは不安だという方や期限が迫っているという方は、お早めにベリーベスト法律事務所 所沢オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|