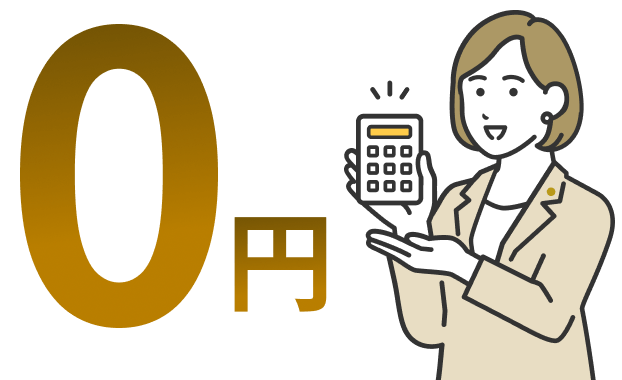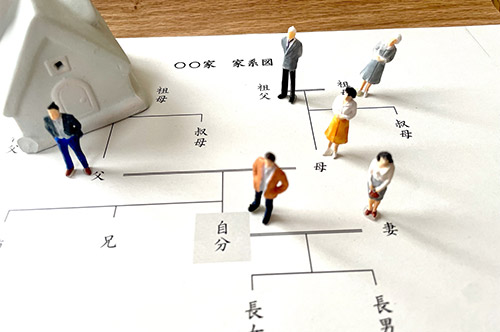相続放棄ができない場合どうしたらいい? 対処法や注意点を解説
- 相続放棄・限定承認
- 相続放棄
- できない
- 場合

亡くなった被相続人が債務を負っていた場合、相続放棄をすることによって、債務の相続を回避できます。
ただし、熟慮期間の経過や法定単純承認などにより、相続放棄ができないケースもあるので注意が必要です。確実に相続放棄を行いたい場合には、相続が発生した後、速やかに弁護士へのご相談をおすすめします。
今回は、相続放棄の概要、相続放棄が認められないケースや対処法、相続放棄を行う際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスの弁護士が解説します。
1、相続放棄とは?
相続放棄とは、相続権を有する者(法定相続人)が行う、遺産を一切相続しない旨の意思表示を意味します(民法第939条)。
-
(1)相続権を放棄する意思表示
相続人は、相続に関して以下の3つのいずれかを選択することができます。
① 単純承認
相続分に従い、遺産を相続する旨の意思表示です。
② 限定承認
遺産のうち、資産を相続しつつ、債務は取得した資産の限度でのみ相続する旨の意思表示です。
③ 相続放棄
遺産を一切相続しない意思表示です。
相続放棄をした者は、当初から相続人にならなかったものとみなされ、被相続人の資産・債務を一切相続しないことになります(民法第939条)。
-
(2)相続放棄をするメリットがあるケースの例
相続放棄をするメリットがあるのは、主に相続財産が債務超過となっている場合です。
相続の対象は、被相続人が死亡時に有した一切の権利義務とされています(民法第896条)。
したがって、相続財産に含まれる資産と債務は、いずれも相続の対象となります。
仮に相続財産が債務超過の場合、相続人はマイナスの財産を相続することになってしまいます。この場合、相続放棄をすることによって、マイナスの財産の相続を回避できます。
また、被相続人や他の相続人との関係性などの問題により、遺産分割に関わりたくないという場合にも、相続放棄をすることが考えられます。相続権を自ら放棄することによって、遺産分割協議に参加する必要がなくなるからです。 -
(3)相続放棄の手続き
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して申述(申立て)を行わなければなりません(民法第915条第1項)。他の相続人に対して「相続放棄をする」などと伝えるだけでは、相続放棄の効果は発生しないので注意が必要です。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
参考:「相続の放棄の申述」(裁判所)
2、相続放棄が認められないケース
以下に該当する場合には、相続放棄が認められない可能性があります。
-
(1)相続開始を知った日から3か月が経過した場合
相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法第915条第1項)。
この3か月間を「熟慮期間」と呼んでいます。
通常は被相続人の死亡を知った時点から熟慮期間が進行しますが、代襲相続や他の相続人による相続放棄などによって、後から自分に相続権が回ってきた場合には、そのことを知った時点が起算日となります。
熟慮期間が経過した場合、原則として相続放棄が認められないので注意が必要です。 -
(2)法定単純承認が成立する場合
以下のいずれかに該当する場合には、「法定単純承認」が成立します(民法第921条第1号、第3号)。
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合(保存行為および短期賃貸借を除く)
- 相続人が、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で相続財産目録に記載しなかった場合(相続放棄をした後も同様)
もし、相続財産に手を付けてしまった場合には、法定単純承認により相続放棄が認められなくなる可能性が高いです。
相続放棄をする予定がある場合には、相続財産の処分等をしないように注意しましょう。 -
(3)申述書類に不備がある場合
相続放棄をする際には、家庭裁判所の指示に従い、所定の申述書類を提出する必要があります。申述書類に不備がある場合には、家庭裁判所によって相続放棄の申述が却下される可能性があります。
3、相続放棄できない場合の対処法
相続放棄が認められないと、思わぬ金額の債務を背負ってしまうことになりかねません。相続放棄ができない可能性がある場合、何か対処法はあるのでしょうか。
-
(1)熟慮期間(3か月)が経過しても、相続放棄は認められる?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間が経過しても、遅れた事情によっては、家庭裁判所の判断によって相続放棄が認められる可能性があります。
やむを得ない事情によって遅れてしまった場合にも、相続放棄を認めずに過大な債務の負担を強いることは、相続人にとって酷だからです。
具体的には、相続財産に借金などの相続債務が含まれていることを全く知らなかった場合、相続債務の存在を知った時から3か月以内に申述を行えば、熟慮期間の経過後であっても、相続放棄が認められる可能性が高いです。
金額の大きな相続債務の存在が判明した場合は、速やかに弁護士へ相談のうえ、相続放棄の検討に着手しましょう。 -
(2)申述書類の不備は補正・追完が可能
家庭裁判所に申述書類の不備を指摘された場合、家庭裁判所の指示に従って補正・追完を行えば、申述書類を受理してもらえます。
ただし、補正・追完には手間がかかるので、極力当初から形式の整った書類を提出することが望ましいです。補正・追完を要しない申述書類の作成は、弁護士にご相談ください。 -
(3)法定単純承認は取り返しがつかない|事前に弁護士へご相談を
法定単純承認に当たる行為をしてしまうと、その後は相続放棄ができなくなってしまいます。後から法定単純承認に当たる行為を撤回することはできないので、取り返しがつきません。
したがって、相続放棄をすべき可能性がある場合には、法定単純承認に該当しないように注意深く行動する必要があります。
その際、できること・できないことの範囲を明確に区別・認識しておくことが大切ですので、事前に必ず弁護士へご相談ください。
4、相続放棄をする際の注意点
熟慮期間や法定単純承認のほか、相続放棄に関しては、以下のポイントに留意しておきましょう。
-
(1)相続財産の調査を漏れなく行う必要がある
相続放棄すべきかどうかを適切に判断するためには、相続財産の調査をもれなく行う必要があります。
資産超過なのか、それとも債務超過なのかを正確に把握することが、相続放棄の要否を判断するポイントになるからです。
特に、被相続人と同居していなかった相続人にとっては、相続財産の全体像を把握することが困難な場合が多いでしょう。相続財産の調査をご自身で行うのが難しい場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。 -
(2)相続放棄は撤回できない
家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うと、その意思表示は撤回することができません。
たとえば、後から高価な相続財産の存在が発覚した場合や、気が変わって相続財産を手元に残しておきたくなった場合などにも、相続放棄が済んでしまっていると、相続財産を手放す必要があります。
相続放棄の際には、後悔することがないように、事前にメリット・デメリットに関する適切な比較・検討を行いましょう。 -
(3)相続放棄の必要書類は、申述人と被相続人の続柄によって異なる
家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う際の必要書類は、申述人と被相続人の続柄によって異なります。具体的な必要書類は、裁判所ホームページ(相続の放棄の申述)から確認できます。
被相続人の配偶者または子の場合、相続放棄の必要書類は比較的少なく済みます。これに対して、直系尊属・兄弟姉妹や代襲相続人(孫・甥・姪など)の場合、多くの書類が必要になる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、必要書類の取得・相続放棄申述書の作成・実際の申述手続きなど、一括して代行してもらうことができます。相続放棄をスムーズに行いたい方は、お早めに弁護士までご相談ください。
5、まとめ
相続放棄は、マイナスの財産の相続を回避するための方法として有効ですが、熟慮期間の経過や法定単純承認などが理由で、家庭裁判所に却下されてしまうこともあります。
相続放棄が認められないと、多額の相続債務を背負ってしまうことになりかねません。確実かつ円滑に相続放棄をするためには、弁護士へのご相談をおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所は、相続放棄その他の遺産相続に関するご相談を、随時承っております。
亡くなった被相続人の債務が判明した方、その他遺産相続についてお悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 所沢オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています